ニコンから一昨日、View NX-i (Ver.1.4.0) 及び Capture NX-D (Ver.1.6.0)のUpdate版がリリースされました。このリリースに伴い Picture Control Utility 2 , Camera Control Pro 2 , Wireless Transmitter Utility , Nikon Message Center 2 も更新されてます。
View NX-i 及び Capture NX-D を更新するには View NX-i & Capture NX-D Ver.1.19.036 をダウンロードして実行すれば更新されます。
更新の大きな理由は11月末発売予定のZ50対応です、その他にも数々の修正が含まれてる様です。
Nikon Capture NX-D Ver.1.6.0 の更新内容
- Z 50 に対応しました。
- 画像にプロテクト設定ができるようになりました。
- カラーコントロールポイントが複数選択された場合でも、テキストボックスに値を入力できるようにしました。
- コントロールポイントのプレビュー上のスライダーにおいて、マウスホイールによる調整を可能にしたことにより、1ステップでの微小量の調整が可能となりました。
- [環境設定]>[表示]>[画像表示]において、速度優先と品質優先を選択できるようになりました。
- クロップが適用された画像のサムネイル表示が低速となる現象について、速度優先モードを選択することによって高速に表示されるように修正しました。
- Capture NX2で編集されたNEF画像をファイル変換した場合に、画像の色味が変わってしまうことがある現象を修正しました。
- フォーカスポイント非表示の状態でクロップと傾き補正を行うと、フォーカスポイントの表示位置がずれる現象を修正しました。
当方は昨日更新しました。問題無く稼働してます。
キャッチアップ画像として本日撮影したノゴマをUpさせて頂きます。
こちらのノゴマ君居心地が良いのか長期滞在中です。
撮影データ:Nikon D5 AF-S Nikkor 600mm f/4E + TC-14EⅢ 露出Mode: Manual 1/500秒 F5.6 ISO: Auto WB: 晴天 RAW
写真1 ノゴマ

写真2 ノゴマ

写真3 ノゴマ

写真4 ノゴマ

写真5 ノゴマ

写真6 ノゴマ

写真7 ノゴマ

写真8 ノゴマ














































































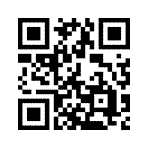 https://marinescape.jp/
https://marinescape.jp/

最近のコメント